みなさんこんにちは
今日は何色の1日でしたか
最近私は、動画作成と動画編集にはまっています
もともとパソコン操作が好きなのと、
YouTubeって統計が取れるのでそれを見て分析するのがとても面白いことが
はまっている理由だと思います
色彩検定を勉強している方向けに
慣用色名について、楽しく覚えてもらえたらいいな~って思い
動画を作ってみました
ただ、動画だと一つ一つのシーンが流れてしまうので
最後まで読めなかったというお声をいただきましたので、
ブログにしてみました
霜降(そうこう)と七十二候
10月23日~10月27日頃 霜始降(しもはじめてふる)
10月28日~11月1日頃 霎時施(こさめときどきふる)
11月2日~11月6日頃 楓蔦黄(もみじつたきばむ)
10月28日~11月1日頃 霎時施(こさめときどきふる)
11月2日~11月6日頃 楓蔦黄(もみじつたきばむ)
四季の色巡り
赤朽葉(あかくちば)
落ち葉が土に朽ちようとする色が朽葉色
紅葉の落ち葉は赤朽葉、黄色の葉は黄朽葉、緑は青朽葉と呼び分け、「朽葉四十八色」というほどバリエーションがあった
襲の色目では表が紅、間に着るのが赤みの黄、裏は黄で、秋が深まると着ないことになっていたそうだ
紅葉の落ち葉は赤朽葉、黄色の葉は黄朽葉、緑は青朽葉と呼び分け、「朽葉四十八色」というほどバリエーションがあった
襲の色目では表が紅、間に着るのが赤みの黄、裏は黄で、秋が深まると着ないことになっていたそうだ
朽葉色(くちばいろ)★
平安時代から用いられた伝統色名
当時は「茶色」という色名がなく、近世以降の茶色に相当する色名として使われていた
伝統色名の中でも特に晩秋の季節感が濃厚な色名で、染、織、襲の色にあり、どれも紅花と支子(くちなし)の組み合わせとされた
襲の色目では表が薄紅、裏が山吹色
★色彩検定2級出題範囲
当時は「茶色」という色名がなく、近世以降の茶色に相当する色名として使われていた
伝統色名の中でも特に晩秋の季節感が濃厚な色名で、染、織、襲の色にあり、どれも紅花と支子(くちなし)の組み合わせとされた
襲の色目では表が薄紅、裏が山吹色
★色彩検定2級出題範囲
パンプキン(pumpkin)
カボチャの果肉のような強い赤みの黄色の色名
日本にも定着したハロウィンは、もとはキリスト教の異教徒であったケルト人の祭日に起源があり、11月1日の万聖節(All Hallow’s Day)の前日の祝日(All Hallow’s Eve)となりHalloweenとなった
日本にも定着したハロウィンは、もとはキリスト教の異教徒であったケルト人の祭日に起源があり、11月1日の万聖節(All Hallow’s Day)の前日の祝日(All Hallow’s Eve)となりHalloweenとなった
栗色(くりいろ)★
栗の実の表皮のような色のことで、「落栗色」とも言われた
中世以降「栗色」「栗皮色」の色名が定着し、江戸時代には「栗皮茶」という染色の色が流行する
赤みを帯びれば「栗梅色」という
平安時代の襲の色目には「落栗」があり、表が濃蘇枋、裏は香色(こういろ)で秋の色目
★色彩検定3級出題範囲
中世以降「栗色」「栗皮色」の色名が定着し、江戸時代には「栗皮茶」という染色の色が流行する
赤みを帯びれば「栗梅色」という
平安時代の襲の色目には「落栗」があり、表が濃蘇枋、裏は香色(こういろ)で秋の色目
★色彩検定3級出題範囲
マルーン(maroon)★
スペイン産の大粒の栗の名前が英語化したもので、初めはイタリア語のマローネ、次にフランス語でマロンとなり、さらに英語のマルーンとなった
英語には栗の実の色の「チェストナットブラウン」があるが、マルーンはそれより赤みのある色をいうようになった
★色彩検定2級出題範囲
英語には栗の実の色の「チェストナットブラウン」があるが、マルーンはそれより赤みのある色をいうようになった
★色彩検定2級出題範囲
柿色(かきいろ)
柿の実のようなオレンジ色の色名で、近世の染色の名前としては照柿がある
柿渋で着色した柿渋色もしばしば柿色と通称されている
柿色の薄い色は「洗柿」でこれより薄いものは「洒落柿」「晒柿」「薄柿」がある
柿の原産地は東洋で、フランス語でもドイツ語でもkakiという
柿渋で着色した柿渋色もしばしば柿色と通称されている
柿色の薄い色は「洗柿」でこれより薄いものは「洒落柿」「晒柿」「薄柿」がある
柿の原産地は東洋で、フランス語でもドイツ語でもkakiという
柿渋色(かきしぶいろ)
柿渋色は単に柿色と言われたが、
柿の実のような黄赤色の染色も柿色だし、団十郎茶の柿渋と弁柄で染めた赤茶色も別名柿色という
柿渋色の衣装を纏った中世の山伏は自由に通行できたので、源義経のように忍びの者が身をやつす際に使われた
後世には歌舞伎の定式幕の色となり非日常の意味を秘めている色になる
柿の実のような黄赤色の染色も柿色だし、団十郎茶の柿渋と弁柄で染めた赤茶色も別名柿色という
柿渋色の衣装を纏った中世の山伏は自由に通行できたので、源義経のように忍びの者が身をやつす際に使われた
後世には歌舞伎の定式幕の色となり非日常の意味を秘めている色になる
サーモンピンク(salmonpink)★
鮭の切り身の色のことで、18世紀にできた色名
魚の肉の色からとられた色名は英語でも他に思い当たるものがなく、
もともと魚の名前からとられた色名そのものがほとんどない
鮭は日本で古くから食用にされ、干して乾燥させた「乾鮭色(からさけいろ)」という色名がある★色彩検定3級出題範囲
魚の肉の色からとられた色名は英語でも他に思い当たるものがなく、
もともと魚の名前からとられた色名そのものがほとんどない
鮭は日本で古くから食用にされ、干して乾燥させた「乾鮭色(からさけいろ)」という色名がある★色彩検定3級出題範囲
鶸色(ひわいろ)★
真鶸の羽の色からつけられた黄色に近い強い黄緑色の色名
日本の色名には動物の毛皮からとられたものは多くないが、鶸色は羽毛からつけられた名前として中世から用いられていた
鶸は寒くなると日本に群れで渡ってくる鳥で、四季の変化に敏感な日本人に冬の到来を告げる使者だった★色彩検定2級出題範囲
日本の色名には動物の毛皮からとられたものは多くないが、鶸色は羽毛からつけられた名前として中世から用いられていた
鶸は寒くなると日本に群れで渡ってくる鳥で、四季の変化に敏感な日本人に冬の到来を告げる使者だった★色彩検定2級出題範囲
竜胆色(りんどういろ)
桔梗と並び日本の秋を代表する色
秋に用いられた式目で、襲の色目では蘇枋と縹、あるいは濃縹と紫などの組み合わせが表裏の色とされた
中国では根が熊の胆(い)より苦いとされ「竜胆」となり、「りゅうたん」が訛ってリンドウとなったという
秋に用いられた式目で、襲の色目では蘇枋と縹、あるいは濃縹と紫などの組み合わせが表裏の色とされた
中国では根が熊の胆(い)より苦いとされ「竜胆」となり、「りゅうたん」が訛ってリンドウとなったという
紫苑色(しおんいろ)
平安の貴族社会で愛好された紫色の色名のひとつ
古名を「のし」といい平安時代には「しおに」ともいった
襲の色目では、薄色と青、紫と蘇枋、蘇枋と萌黄など諸説あり、秋に用いる式目とされる
俳句でも秋の季語となっている
古名を「のし」といい平安時代には「しおに」ともいった
襲の色目では、薄色と青、紫と蘇枋、蘇枋と萌黄など諸説あり、秋に用いる式目とされる
俳句でも秋の季語となっている
桔梗色(ききょういろ)★
秋の季節を代表する青紫の伝統色名
古名を「きちこう」「きこう」ともいう
襲の色目では表が薄紫、裏が青
または表が二藍、裏が濃青など
いくつかの説がある
万葉集で山上憶良が秋の七草の一つにあげた朝顔は桔梗のことだとの定説がある
★色彩検定3級出題範囲
古名を「きちこう」「きこう」ともいう
襲の色目では表が薄紫、裏が青
または表が二藍、裏が濃青など
いくつかの説がある
万葉集で山上憶良が秋の七草の一つにあげた朝顔は桔梗のことだとの定説がある
★色彩検定3級出題範囲
参考図書
『色の名前事典507』/福田邦夫
『色彩検定公式テキスト』
『花の色図鑑』/福田邦夫
『すぐわかる日本の伝統色』
『日本の伝統色』
『日本の色 世界の色』
『色の名前』
『色で巡る日本と世界』/色彩文化研究会・城一夫
『和の色ものがたり』
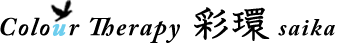
コメントを残す